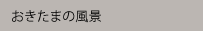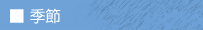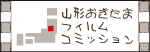高校生の私は、冬の間は遠くの町に下宿していた。日曜日の夕方、下宿に帰るために駅に向かう途中で、スコップを担いでくる大人達とすれ違った。鉄道の除雪隊であり、母もその中にいた。
「行ぐなが?」 「うん」 「気つけてな」
僕は母と目を合わせるのも恥ずかしく、その時の母の顔を覚えてはいない。が、せつない感情がこみ上げてきたことを覚えている。男たちが出稼ぎに行く冬の間、家を守り暮らしを守るのは女の肩にかかっていた。お婆ちゃん子であった私が、記憶に残る母の顔はいつも日焼けした顔であった。
「除雪人夫の頼みに来られると嬉しくて行ったもんだっけなー。」と、窓の外を見ながら何度も同じことを繰り返す。老いた母の顔を見るのも辛いものがあり、ただ「ありがとう」と心の中で繰り返すのみである。
【写真提供:山形鉄道(株)】